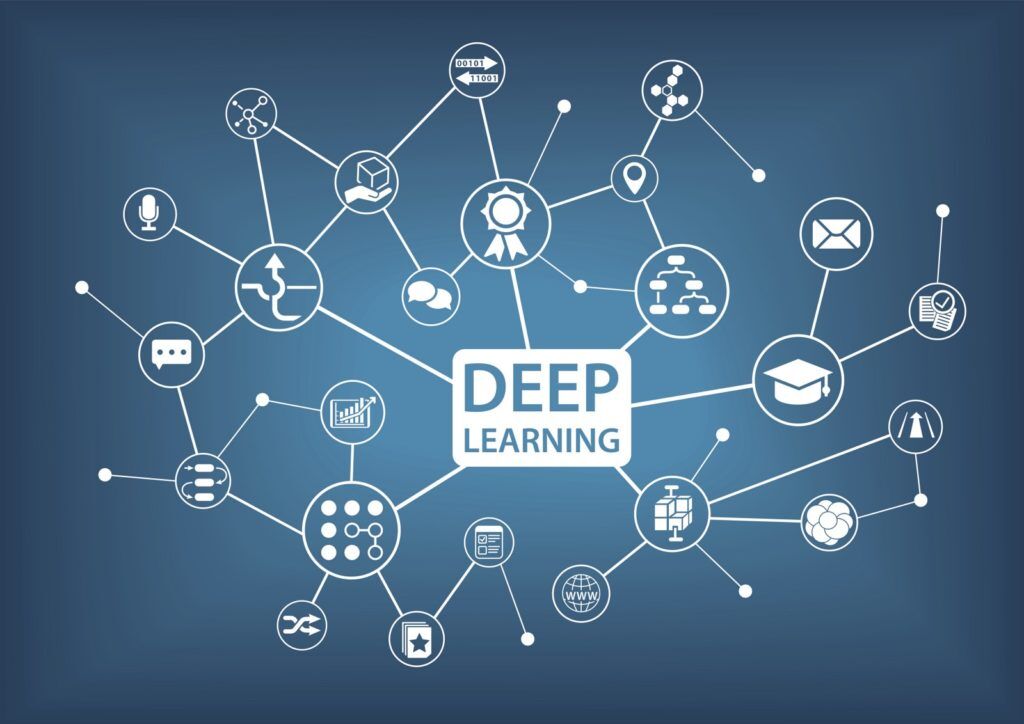【2025年最新版】公認会計士必見!AIツールで監査業務を革新する完全ガイド – 効率化から将来性まで徹底解説
はじめに
公認会計士業界では、AI(人工知能)の活用が急速に進んでいます。KPMGジャパンが提供する会計論点スクリーニングサービスでは、契約書などの大量の資料をAIによって迅速に分析し、重要な会計論点を特定する支援を行っています。また、人材採用難を解決する経理特化型AI「Deep Dean」が日本の公認会計士試験問題(短答式)で満点を記録するなど、AI技術の進歩は目覚ましいものがあります。
日本公認会計士協会(テクノロジー委員会)では、2024年8月9日に「テクノロジー委員会研究文書第11号「監査におけるAIの利用に関する研究文書」」を公表し、監査業務におけるAI活用の指針を明確化しています。
本記事では、公認会計士におすすめのAIツールを詳しく解説し、実際の活用事例から導入時の注意点まで、包括的にお伝えします。
公認会計士業務におけるAI活用の現状
AI導入の背景
監査現場の作業量は年々増加しており、生産性の向上が求められ、また、監査のステークホルダーからの期待に応えるための品質向上についても課題があるという状況の中で、AI活用への期待が高まっています。
業界の変化要因
- 監査業務の複雑化と作業量の増加
- COVID-19の影響によるリモートワーク推進
- デジタル化の進展
- ステークホルダーからの品質向上への期待
AIでできること・できないこと
AIが得意とするのは,あらかじめ定められたルールに基づいて、指示された業務を忠実に実行することです。一方で、AIは過去のデータを蓄積し、そこから答えを出すことはできますが、自身で何か意思決定・判断をすることはできません。
AIが得意な業務
- 帳票突合や帳簿突合などは機械的な作業なので、その結論の導出のために人間の意見は必要ありません
- 大量データの分析・処理
- 定型的な監査手続きの実行
- 異常値の検出・アラート
公認会計士にしかできない業務
- 監査クライアントから直接相談があったときのコミュニケーションや、高度な判断が求められる場面では、定められたルールに準拠するAIのみでは対応できません
- 不正の発見・判断
- クライアントとの信頼関係構築
- 複雑な会計処理の判断
おすすめ公認会計士向けAIツール12選
大手監査法人開発のAIツール
1. Audit Suite Text Reviewer(トーマツ)
トーマツは、日本語の契約書等の専門文書と公認会計士等が有する検討のノウハウをAIに学習させることで、専門文書から監査に必要な情報の特定・抽出を行い視覚的に表示するAIツール「Audit Suite Text Reviewer」(AS Text Reviewer)を開発し、2022年9月から順次導入を開始しました。
主な機能
- 契約書等の専門文書から監査に必要な情報の自動抽出
- 会計・監査に影響する重要な項目の漏れない特定
- 熟練公認会計士のノウハウをAIに学習
- 視覚的な情報表示
向いている業務
- 契約書レビュー業務
- 重要な取引条件の把握
- 会計処理検討の効率化
2. KPMGジャパンの会計論点スクリーニングサービス
KPMGジャパンが提供する会計論点スクリーニングサービスでは、契約書などの大量の資料をAIによって迅速に分析し、重要な会計論点を特定する支援を行っています。
主な機能
- 大量資料の迅速な分析
- 重要な会計論点の自動特定
- 監査効率の大幅向上
- データ分析の短時間実施
3. あずさ監査法人のAI監査技術
有限責任 あずさ監査法人が提供するAI技術は、監査対象のデータ全件を精査する能力を持ち、監査の品質向上にも寄与しています。
主な機能
- 監査対象データの全件精査
- 従来の試査から精査への転換
- 監査品質の向上
- 網羅的なデータ検証
4. EY新日本のデジタル監査体制
EY新日本有限責任監査法人は、生成AIを活用したデジタル監査体制を強化し、AIガバナンスに関する指針の導入を予定しています。
主な機能
- 生成AI活用監査体制
- AIガバナンス指針
- デジタル監査プロセス
- 品質管理の強化
5. PwC Japanのリース会計支援
PwC Japan有限責任監査法人では、リース会計基準適用支援サービスにおいて契約書をAIによって自動判定する仕組みを導入し、プロセスを効率化しています。
主な機能
- リース契約の自動判定
- 契約書分析の自動化
- IFRS16対応支援
- 会計処理判断の効率化
汎用AIツール(公認会計士業務活用)
6. ChatGPT(監査業務活用)
ChatGPTは、監査調書の下書き作成、複雑な会計基準の解釈支援、財務分析レポートの作成等に活用できます。
主な活用方法
- 監査手続書の下書き作成
- 会計基準の解釈支援
- 財務分析レポート作成
- 監査報告書のドラフト作成
料金プラン
- ChatGPT Plus:月額20ドル
- ChatGPT Team:月額25ドル/人(年間契約)
- 無料版も利用可能
7. Claude(文書解析特化)
複雑な財務諸表や監査資料の分析、長文契約書の要約等に優れた性能を発揮します。
主な機能
- 長文財務資料の精密分析
- 契約書の重要ポイント抽出
- 複雑な会計処理の解説
- 監査論点の整理
8. Microsoft Copilot(Office連携)
ExcelやWordなどのOfficeアプリケーションと連携し、監査調書作成やデータ分析を効率化します。
主な機能
- Excel上でのデータ分析支援
- Word文書の自動作成支援
- PowerPoint資料作成支援
- Teams会議の議事録自動作成
専門特化型AIツール
9. Deep Dean(経理特化AI)
経理シンギュラリティを実現する経理特化型AI「Deep Dean」が、FASS検定(経理・財務スキル検定)やUSCPA(米国公認会計士)に加えて、公認会計士試験でも、高度な会計・監査の知識において卓越した性能を発揮しています。
主な機能
- 公認会計士試験レベルの知識対応
- 高度な会計・監査知識の実証
- 日本基準・国際基準への対応
- 実務への展開加速
10. AI-OCRツール(監査証憑読取)
大量の監査証憑を自動でデジタル化し、データ抽出を行います。
主な機能
- 領収書・請求書の自動読取
- 契約書のテキスト化
- 手書き文字の認識
- 監査証憑のデータベース化
11. データ分析特化AIツール
財務データの異常検知、不正発見支援、業界比較分析等を自動化します。
主な機能
- 異常値検知・アラート
- 不正の兆候発見
- 業界ベンチマーク比較
- 予測分析
12. 監査調書作成支援AI
監査手続きの記録や調書作成を自動化・効率化します。
主な機能
- 監査手続の自動記録
- 調書フォーマットの統一
- 品質チェック機能
- 過年度比較分析
公認会計士業務でのAI活用事例
監査手続きの効率化
AI監査ツールが十分な精度に達するまでは、監査人がツールのテスト結果をチェックして効率的に精度を改善することが求められる。しかし、ツールの精度が100%に近づけば、監査人はAI監査ツールに依拠することができる。
具体的な効果
- 証憑突合作業の自動化
- 全取引データの網羅的チェック
- 内部統制テストの効率化
- リスク評価の精度向上
データ分析・不正発見
データのつき合わせやチェックにおいて、人間が行う場合はピックアップして確認することになりますが、AIの場合は全件チェックが可能です。
活用領域
- 異常取引の検出
- 関連当事者取引の特定
- 売上計上の妥当性検証
- 経費の適切性チェック
契約書・文書分析
重要な項目は多岐にわたることが多く、会計基準ごとに視点も異なるため、複雑かつ長文の契約書等から必要な情報を漏れなく識別するためには知識と経験が求められますが、AIがこの業務を支援します。
効率化の効果
- 契約書レビュー時間の短縮
- 重要条項の見落とし防止
- 会計処理判断の迅速化
- 監査リスクの軽減
財務分析・レポート作成
AIを活用した財務分析により、より深い洞察を短時間で得られます。
活用例
- 財務比率分析の自動化
- 業界比較レポートの生成
- 経営指標のトレンド分析
- 将来予測モデルの構築
AI活用時の注意点とリスク
守秘義務・機密性の課題
監査法人の中で独自にAIを開発し、法人内の利用に限定するのであれば、守秘義務はクリアしやすいでしょう。ただその場合は、ChatGPTのような公開されているAIほどの性能が出ない可能性があります。
対策方針
- 機密情報の外部AI入力禁止
- 法人内専用AIシステムの構築
- データ暗号化とアクセス制限
- 監査クライアントとの契約条項確認
AI判断の限界と責任
監査判断は、誰が見てもセーフと言えるものから、誰が見てもアウトまで、無数の段階があります。このような複雑な判断において、AIの限界を理解することが重要です。
留意点
- AIの判断は最終的に人間が検証
- グレーゾーンの判断は公認会計士が実施
- AI出力の根拠確認の徹底
- 監査意見形成は人間が責任を持つ
法的・倫理的配慮
AIの透明性や公平性の確保に加え、データの取り扱いに関するプライバシー保護やセキュリティ対策も厳格に求められます。
遵守事項
- 監査基準との整合性確保
- AI利用の透明性確保
- データ保護法制の遵守
- 職業倫理規定の維持
技術的制約とリスク
生成AIの透明性や信頼性の確保が欠かせません。AIが提供するデータや洞察の根拠を明確化することが求められる中、監査法人や被監査会社が内部統制を強化し、AIガバナンス体制を確立する必要があります。
リスク管理
- AIの誤判定リスク
- データの偏りによる影響
- システム障害時の対応
- 継続的な学習・更新の必要性
AI導入成功のポイント
段階的導入戦略
検証フェーズ
- 限定的な業務での試験導入
- AI精度の検証と改善
- スタッフの習熟度向上
拡張フェーズ
- 適用範囲の段階的拡大
- 業務プロセスの最適化
- 品質管理体制の構築
運用フェーズ
- 全面展開と継続改善
- パフォーマンス評価
- 新技術への対応
スタッフ教育・研修
理化学研究所の報告書でも指摘されていますが、AIと対立するのではなく、むしろ積極的に活用することが、公認会計士に求められるようになるでしょう。
研修内容
基礎研修
- AI技術の基本理解
- 監査業務への応用方法
- リスク認識とガバナンス
実務研修
- 具体的ツールの操作方法
- AI出力の適切な解釈
- 品質管理手法
ガバナンス体制の整備
新たなリスク管理フレームワークの構築が不可欠です。従来の監査リスクに加え、AI特有の課題、例えば誤った情報生成や不完全なデータセットによる誤差のリスクに対応する必要があります。
必要な取り組み
- AIガバナンス委員会の設置
- AI利用ガイドラインの策定
- 継続的監視システムの構築
- インシデント対応体制の整備
公認会計士の将来性とキャリア展望
AIとの共存による価値創造
AIの導入は、公認会計士が新たな業務領域に進出するための大きなチャンスでもあります。例えば、ビッグデータを活用した高度なデータ分析や、持続可能性を確保するための非財務情報の評価、企業のリスク管理に関するサポートなど、これまでにない役割が求められています。
新しい業務領域
- ESG監査・保証
- デジタル監査コンサルティング
- データアナリティクス
- リスクマネジメント支援
必要なスキルの変化
AI時代において、公認会計士にはデータ分析スキルがますます重要性を増しています。AIやRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入により、膨大なデータを効率的に処理できる環境が整う一方で、それを活用して意思決定やリスク分析に結びつける力が求められています。
重要なスキル
技術的スキル
- データ分析能力
- AIツールの活用力
- デジタルリテラシー
専門的スキル
- 高度な判断力
- リスク評価能力
- 複雑な問題解決力
ソフトスキル
- クライアントコミュニケーション
- プロジェクトマネジメント
- 変革リーダーシップ
キャリアパスの多様化
AI化によって公認会計士の働き方が多様になれば、企業内公認会計士・ベンチャー企業の役員として活躍できますし、公認会計士自身がビジネスを立ち上げて社会にクリエイティブなサービスの提供も増えてくるでしょう。
新しいキャリア選択肢
- AI監査システム開発・運用
- データサイエンティスト
- デジタル変革コンサルタント
- テクノロジー企業の財務責任者
2025年のAI動向と将来展望
技術的進歩
生成AI技術の発展
- より高精度な文書分析
- 自然言語での監査手続き指示
- 多言語対応の強化
監査プラットフォームの統合
- 統一されたデータ形式
- システム間の連携強化
- クラウドベースの監査環境
規制・基準の整備
大手監査法人を中心にAIを利用した監査ツールの開発が進められ、実際に監査実務の現場への導入も進んでいることから、監査において利用されるAIに関する理解を更新し、具体的な活用方法及び課題について改めて整理する必要性が高まっています。
期待される動向
- AI監査基準の策定
- 国際的なガイドライン統一
- 品質管理基準の更新
- 教育・研修制度の整備
業界全体の変革
短期的見通し(1-2年)
- 定型業務のさらなる自動化
- AI監査ツールの標準化
- スタッフのスキル転換加速
中長期的見通し(3-5年)
- 監査手法の根本的変革
- 新しい保証業務の創出
- グローバルな監査プラットフォーム確立
まとめ
公認会計士業務におけるAI活用は、もはや選択肢ではなく必要不可欠な要素となっています。当協会の関根会長が、公認会計士の本質はAIに代替できないことを語りますが、同時に適切なタイミングで、適切な相手に、適切に問いかけることは、人間にしかできないスキルであるため、公認会計士の仕事の本質的な部分はAIには奪われない、つまり「なくならない」ということも明確です。
成功のカギ
- 適切なAIツールの選択と段階的導入
- 守秘義務と品質管理の両立
- 継続的な教育とスキル向上
- AIガバナンス体制の確立
- 新しい価値創造への積極的挑戦
公認会計士の業務の本質は「会計というツールを通じて会社の状況を見極め、サポートや意思決定をすること」であり、これはAIが苦手とする分野です。AIを適切に活用しながら、人間にしかできない高付加価値業務に集中することで、公認会計士はより重要な役割を担うことができるでしょう。
これからの公認会計士にとって、AIとの協働は競争優位の源泉となります。今こそ、AI時代に対応した新しい監査業務のあり方を模索し、準備を始める時です。
参考リソース
- 日本公認会計士協会 公認会計士業務とAI
- 各監査法人のAI活用事例
- テクノロジー委員会研究文書
- AI監査ツール公式サイト
本記事は2025年8月時点の情報に基づいています。AI技術や監査基準は日々変化しているため、最新情報の確認をお勧めします。
■プロンプトだけでオリジナルアプリを開発・公開してみた!!
■AI時代の第一歩!「AI駆動開発コース」はじめました!
テックジム東京本校で先行開始。
■テックジム東京本校
「武田塾」のプログラミング版といえば「テックジム」。
講義動画なし、教科書なし。「進捗管理とコーチング」で効率学習。
より早く、より安く、しかも対面型のプログラミングスクールです。
<短期講習>5日で5万円の「Pythonミニキャンプ」開催中。
<オンライン無料>ゼロから始めるPython爆速講座